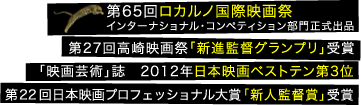コメント
モノクロなのに、いろんな色が観えてくる。その目で確かめて。
新井浩文(俳優)
美しい映画だ。しかも、哲学的でヨーロッパ的なセンスに溢れた、新しいレベルの日本映画に達しようとしている。それは、人は想像力を命の糧にしてやっと生き延びているという、聖なる仕組みを語り口にしているからだろう。
足立正生(映画監督)
知らぬ間に土地は荒れ、知らぬ間にフィルムも映画も消えていく。いまも原発の止まらぬこの日本で、私たちは選ぶことなどしてこなかったのだ。しかし『Playback』を観るとヤツラが好き勝手に滑ってくるから、気分を出してもう一度って嬉しくなる。
相澤虎之介(空族/映画監督)
美しいモノクロフィルムに映る、もう若くはない男たちの美しいこと。ムラジュンのこの「顔」は一見の価値有り(もちろん他の役者さんたちも素敵だけど!)。
夢なのか現実なのか現在なのか過去なのか。もしかしたら未来なのか。日本映画かアメリカ映画なのかすらわからなくなるこの作品こそが三宅監督が作った未来なのかもしれない。そんなことにゾクゾクできる映画。あと、20年ぶりくらいにスケボーやってみたくなった!
渥美喜子(gojo)
語らずとも漂ってくるその雰囲気、ただそこにある匂い、なんなんだろう?この妙なリアル感。
やる気と頑張りで夢を掴めた時代は終わり、この映画には今のリアルな夢が存在していました。
「じゃぁ、はじめましょう」
「お願いします」
池永正二(ミュージシャン あらかじめ決められた恋人たちへ/シグナレス etc.)
1本の映画作品を作ることはただでさえ冒険だ。まず必要な資金、そしてスタッフ、キャストを揃えて撮影にこぎ着ける……気が遠くなるくらいの冒険だ。『Playback』の冒険は、映画についてのそんな冒険を最初から凌駕している。それは、映画を彩る鮮やかな色彩を黒く染め、直線的に語られるべき物語の時制を、死臭を導入することで混乱させつつ、映画の未踏峰の頂点に立とうとする信じがたい大冒険だ。
梅本洋一(映画批評家)
『Playback』は、ここ数年ふたたび息吹を取り戻したようにみえる若手日本映画──ロカルノはその国際的なショーケースとなった──からの良い報せであり、見事なサプライズだ。三宅唱はその処女長編で(訳注:『Playback』はロカルノ国際映画祭より「処女長編」と指定された)、芸術性と知性の堂々たる成熟を示してみせる。弱冠28歳のこのシネアストが語るのは、夢と現実のあいだでの、逃避と後悔の狭間での、過去への帰還、時間の旅という物語だ。モノクロで撮影され、危機を迎えたひとりの映画俳優(冒頭のシーンはアフレコのスタジオであり、彼は監督からダメ出しを受けている)を演出する『Playback』は、ある種のポストモダンの伝統にはっきりと身を置く。つまり映画の登場人物たちと世界を、荒唐無稽な仕掛けに組み入れること。シネフィリーで、映画批評とともに育った監督とプロデューサーは、ヨーロッパ映画の遺産を理解してきたと同時に、たとえば青山真治の映画もまた、自分たちの血肉としてきた。この作品が我々を強く打つのは、穏やかさと繊細さによって、非常に大きなメランコリーと非常に強い同時代性を混ぜ合わせるその才と、理論的な話法と同時に非常に印象主義的な映画を、普遍的なテーマとエモーションに繋げるその才だ。『Playback』はプルーストとドゥルーズと、そしてスケートボードのあいだの不慮の出会いを組織した。三宅唱によって優雅に撮られた、主人公が辿る故郷へのあの道。あれこそ時間であり運動であり、そう、映画なのだ。
オリヴィエ・ペール(前ロカルノ国際映画祭ディレクター)
「この世界に流れる時間は決して均一ではないのだ」ということを、こんなにハッキリと教えてくれる映画を初めて見た。エンディングに向かって加速度的に増していく時間の速度のエネルギーは、いま僕達が「世界」だと思い込んでいるモノの輪郭をあっさりと破壊して遠くに突き抜けていく。
大森克己(写真家)
誰が見てもカッコ良くて、なおかつキュートで、それでいてとても不気味なのに、終始さわやか。そんな奇妙かつ大らかなバランス感覚で映画を作ることが出来るだなんて……。
大畑創(映画監督)
生まれて死んで甦る。そんな感じがたまにある。だから、『Playback』を観て、なにかを探している自分の感情が、ハッとした、すごく。
夢のような話で、夢がある話だった。
高良健吾(俳優)
これは俳優から監督へ宛てた手紙。
村上淳が三宅唱に宛てた手書きのたより。
筆圧は確かにある。
この映画のなかに活かされている。
柴田剛(映画監督)
21世紀の「新しい波」到来を確信させる見事なモノクロ画面。すべてのショットは画面としてどれもこれも完璧で揺るぎがない。しかも不思議なことに、それらの集合は決してバラバラにならず、力強い流れをつくり出す。
緻密でありながら、直感的でもあるこの映画の文体に触れると、もはや観るものはかたときも目を逸らすことはできない。なぜなら、そこには「物語」に代わるべき、より直接的で、より純粋なサスペンスが横溢しているからだ。
鈴木了二(建築家)
映っているものは多分、役者の芝居の筈なのだが、
それが演技を超えた底知れぬ何かとして伝わって来る。
演者とスタッフと場所が一つの塊になったとき生まれる奇跡。
今、日本という地に苦難を感じている映画が多い中で、
一気に世界へ通じる映画が現れたと思った。
瀬々敬久(映画監督)
モノクロームが語るファンタジー。前作『やくたたず』は冷たいモノクロームだったが、今回は同じモノクロームでもとても暖かかった、何故かぬくもりを感じた。多分、もはや、僕の目にはカラーに映ったのだ。そんな、映画体験だった。
染谷将太(俳優)
あまりに心地よくて、映画の世界から抜け出せなくなりました。ずっとplaybackしていていただきたい!
滝藤賢一(俳優)
35mmB/Wフィルムで焼かれた、日本で最後の映画になる、のか、ならないのか。僕たちはそんな時代に直面している。何度playbackしたところで人生なんて何も変わらないことぐらい知っているけれど、映写されることで傷つき、昨日と同じ繰り返しのようでいて、二度と同じ条件でみることができないフィルムそのものみたいな、その小さな変化ぐらいは信じてみてもいいはずだ。Playback!
月永雄太(キャメラマン)
日本映画史上、今ほど不幸な時代がかつてあっただろうか。そしてそれは、誰もが作る事が可能という諸刃の剣のような希望と背中合わせにある。“今”がどのような意味を持ったのかはいずれ語られるか、いや忘れられるだろう。三宅唱はそんなどうでもいいチンケでクソな事とは全く関係なしに現れた。
そして『Playback』はこの先長く語られ、時と共に変化し成長していくだろう。慌てる事はない。どうしても今観なければいけないということもないほどの風格を持つ、もはや名作だ。
富田克也(空族/映画監督)
世にある「白黒映画」という俗称はいわば印象なのであって、その画面を占める色はおおかた灰色であるというのが正確なところだろう。三宅監督の素晴らしい聡明さは、世界から色彩を剥奪(灰色化)することで俳優に迫ろうとしたという演出上の意志にあるばかりでなく、さらに、その俳優たちに純白と純黒の衣装を身に纏わせることでむしろ「着色」してみせたことに顕著なのではないか(つまり全身純白の新郎新婦の登場は物語上の必然などではなく、灰色への着色の極例)。そして学ランや礼服(と白いシャツ)という純白純黒の時間を往来するこのタイムスリップ映画は、同時に路上の映画でもあって、アスファルトという本来的に灰色である背景のなか、その聡明さがやはり純白純黒とともに際立ってくるのだ。とりわけ頻発される俯瞰のロングショットにおける、くっきり色彩的に突出した俳優たちの姿を見て確信させられた。
あと、「きみ遠藤くんか。俺も遠藤つうんだよ」というリアルかつ無意味な偶然や、実家の鍵が玄関前の花の中に隠してあるといういかにも現場発で予想外なアイディアの好例を見ると、この映画の撮影現場に参加したすべての人々の気持ちの豊かさを知る思いがした。
冨永昌敬(映画監督)
見事な役者陣のアンサンブルとラフで巧みな映像構成で、素敵な多元宇宙を感じさせてくれる人生讃歌に乾杯! 新しい日本映画の才能の息吹を感じさせる傑作だ!
中原昌也(ミュージシャン/作家)
水戸が舞台のこの映画を僕がはじめて観たのは水戸だった。
地元スケーター風貌の三宅監督とモノクロームなプレイバックは、妙にフィクションと現実が交差する。
物語には必ず始まりがあって、終わりがある。
蓮沼執太(音楽家)
これほどまでに大胆にして繊細な新人監督の作品が平成日本に登場したことは奇蹟としか思えず、それに立ちあうことの僥倖をまずは無条件に肯定しておく。
蓮實重彦(映画評論家)
40代を前にして「老い」の予感が俳優を襲い、それ以来俳優のほとんど負けの決まった戦いが始まる…。『Playback』はまるで『オープニング・ナイト』が現代に再生されたようだ。村上淳/三宅唱の闘いは、ローランズ/カサヴェテスのそれと軌を一にしている。生きること、そのために何度でも演じる(生き直す)こと。しかし、『Playback』の闘いは単なる苦闘ではない。耐え抜くのではなく、すり抜けるのだ。少し猫背でスケボーに乗るムラジュンの姿が「パフォーマンス」とは過剰な生ではなく、生との調和であることを観客に示す。そのとき、映画に訪れるよろこび。
濱口竜介(映画監督)
この前、酔っ払いすぎて記憶なくした時とリンクしたす。白くて淡い感じ。そんなこと、今までなかったのに。もう年をとったんだなー。。(しみじみ)P
PUNPEE(ラッパー/DJ)
高校生にはとても見えない老け顔の三人組が学ランを着続け、それを互いに許し合っているという厚かましき事態。老け顔/学ランの時間の齟齬が白/黒の光学的それとして捉えられる。『やくたたず』でのこの試みをそっくり反復しつつ、本作はさらなる齟齬でそれを裏打ちする。40才を前にした男が高校時代を生き直す様を20代後半の若造監督が訳知り顔で描くその厚かましさ。三宅映画の特異性は、前未来時制に定位したその語りによって未来/過去を短絡させ映像を生ける現在の軛から解放した点にではなく、厚かましさの累乗を時間の技術にまで昇格させた点にある。モノクロームは慎み深い? そんなことを言っているから映画は停滞するのだ。『Playback』は我々にそう告げている。
廣瀬純(映画批評家)
タイトルの出方がいいんだよね。トントントンとキックが軽くリズムを刻んで、一瞬のタメがあって、そこにパコーンというスネアの音が聴こえる感じ。まさに何かの始まり。「Playback」なんてタイトルだけど、新しい何かが今まさに始まった、そんな始まりの歓びとそれ故の痛みが溢れてる。始まりは繰り返すばかりで終わらない。その残酷さ。
樋口泰人(映画批評家/boid社主)
才能ある若手は寝ていてほしい。そんな、嫉妬深い私の黒い祈りも届かず、傑作『やくたたず』の三宅唱監督は、堂々たる新作『Playback』を撮りあげてしまった。ベテランを起用した(ベテランに起用された?)この新作で、三宅監督は重圧に負けず、その独特な映画世界を着実にスケールアップさせてきた。
モノクロームの映像はスタイリッシュでかっちょいい迷路を見るようで、しかし、その迷路をさまよう人たちは決してスタイリッシュでもかっちょよくもなく、人間クサく愛おしい。スクリーンを満たす鼻白むほど爛漫なノスタルジーを前に、これほど骨太な物語が仕掛けられる作家さんだったのかと驚いたりもした。
実力ある俳優たちと芯のぶれない若い才能の幸福な出会いに、今日も私は苦虫を噛み潰したような笑顔で精一杯の賛辞を送るのである。
深田晃司(映画監督)
28歳(撮影当時26歳)の新人監督が本格的なデビュー作で人生の曲がり角にさしかかったアラフォーのおっさんを撮る。しかも、ガキには絶対担いきれない最高にクールな白黒の画面で。
幼さばかりがもてはやされる現代に今、『Playback』とともに殴りこみをかける三宅唱は、25歳で『市民ケーン』を撮ったオーソン・ウェルズがそうであったように〈事件〉である。
藤井仁子(映画批評家)
そういえば、前作の『やくたたず』でも寄稿を書いたものの、提出が間に合わなかった記憶がある。これを書き始めるにあたって、上映当日に観客に配布されたコメント一覧を見て、口惜しく思ったのを思い出した。それは『やくたたず』という映画をある種の柵で囲うような、観客を制限をしてしまう印象を受けたからだ。映画を続けていく上で同志とともに切磋琢磨することは必要だと思うし、あえてパブリックイメージを作ることも重要だと思いながらも、ぼくは三宅唱にはもっと見知らぬ人まで巻き込んでいけるポテンシャルを感じていただけに、これは勿体無いと思った。すでに三宅唱は『やくたたず』の時点で、その映画の評価以上に、嫉妬するくらいの能力を見せていたように思う。
だから村上淳さんが三宅唱に会って映画を作ることになった、と聞いた時点で、同業者として、これはやられたと思った。三宅唱の能力を認めた上で、その柵を遠くまで広げる人物が早くも現れた訳で、誰にも気が付かれないように静かに動揺した後、三宅唱は果たしてこの機会にどうアプローチするのかと思いを巡らせながら、兎にも角にも映画の完成を楽しみにしていた。
ここまで書いて今だに『Playback』に言及していないのもどうかと思うが、評論は他の方に任せるとして、ぼくの映画を観た感想を一言で言うとすれば、三宅唱は絶倫だと思った。『Playback』のことを冷静に考えると、ちょっと思惑が間違うと恥ずかしくて自粛しかねないような展開なのに、全く気まずさを感じさせることなく真正面から堂々と(しかも格好良く!)やってのける演出と、それを全面的に信頼して出演された役者の素晴らしさに全編が満ちている。よく中折れしないもんだと思いながら、それは若さではなく才能なんだと驚かされる。ぼくはやはり同業者として、この奇跡のようなセッションを表層的なことで語ることはできない。この映画には足りない面もあるかもしれないが、その不完全さを内包した上で、ここまで他人を信頼し、また信頼された関係において作り上げた、硬派な意思を持つ映画を見ると、現在の状況でこれ以上に観客へ真摯に歩み寄る方法はないと思えて、三宅唱の選択の確かさに感動するとともに、ぼくは彼のポテンシャルが掘り起こされる快感を得た。間違いなく『Playback』は映画事変である。そして世間が気がついたそのうちに、絶倫三宅唱はまたすぐに映画を企みだすに違いない。
真利子哲也(映画監督)
この旅にも終わりがある。そう誰もが思った311を経て、初めてスケートボードに乗った少年のそれのように、辿々しくも確信に満ちた運動からはじまるこの113分間のヒビ割れた旅路の果てに、あなたは、過去が未来であり、現在が永遠であり、ここと二十億光年のかなたが同じであるかのような生と新たな旅のはじまりを発見するだろう。
宮崎大祐(映画監督)
すべてわかったうえでそうしているのだろうと思わずにいられない、そんな静かな知性を一挙手一投足から感じさせる村上淳は、しかし、ともすると、あれ、このひとホントにさ迷ってるのかな、と不安になってしまうような無防備さをさらしたりもする。一体どちらなのだろう。わかっているのか、わかっていないのか。芝居なのか、天然なのか。不自由なのか、自由なのか。終わっているのか、これから始まるのか。
過去と現在を行き来し、時間をループさせる『Playback』の不思議な時空間の中で、作り手たちが捉えようとしたのは、それら二項の間の微妙な、見えるか見えないかの振幅や揺らぎだったのだと思う。少年的な無垢さと中年的な疲れを共存させる村上淳だからこそ、この試みに確かな説得力を与えることができたのではないか。監督との共同作業で生み出されたこのキャラクターの魅力は曰く言い難いが、僕にとってはたとえば天才レスラー武藤敬司を彷彿とさせるものだった。とぼけているがかっこよく、予想不可能だが強い覚悟も感じさせる。
前作『やくたたず』といい『Playback』といい、一見したところ煮え切らないような、とても前向きとは思えない題名を自作につけた監督・三宅唱は、いま新たに映画作家としてのキャリアを始めるために慎重な思索を重ね、そして驚くべき開始点を探り当てた。
三浦哲哉(映画批評/研究)
『Playback』は今を肯定するタイムマシーンだ。
時間を大胆に操り、そうではなかったかもしれない「可能性」を通過し、最後には「真実」を教えてくれる。
この実験装置は発明だと思う。三宅さん、あなたもしや…ドラ○もん!?
森岡龍(映画監督/俳優)
十代の終わり頃。アメリカ映画から受けた“疲れてるのにカッチョイイ”匂いが『Playback』からは漂ってきました。俺よりも若い監督だし、最新作なのに何故だか懐かしかったです。
山下敦弘(映画監督)
日常に良くある話と景色…Playback…。
日常だから感じるモノがある。
モノクロ世界の緊張の中に、鮮やかな色が見える。
35mmフィルムの中に込められた魂は東から登る太陽を逆戻しするようなパワーがある。
村上淳、渋川清彦の演技は本人自身の青春時代を懐かしみ、思い返しながら、今の自分自身の成長を噛み締めて楽しんでいる。
Playbackとは、ある意味「成長」だ。
人は成長するのだ…。
いや、成長しなければならない。