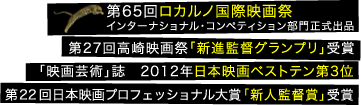三宅唱監督 インタヴュー
 この企画はどのような経緯で始まったのでしょう?
この企画はどのような経緯で始まったのでしょう?
三宅:主演俳優の村上淳さんが、前作『やくたたず』(10)をとても気に入ってくれ、所属事務所の「ディケイド」のスタッフにも勧めてくれたんです。数日後に事務所の代表の方も含めてみんなで一緒に夕飯を食べて、映画の話をしたり、楽しい時間を過ごしました。その翌日には「映画を一緒に作ろう」ということになり、それで企画がスタートしたんです。
 『やくたたず』について、少し説明してもらえますか?
『やくたたず』について、少し説明してもらえますか?
三宅:『やくたたず』は僕の最初の長編映画です。大阪市が主催するCO2(シネアスト・オーガニゼーション・大阪)という、若手のインディペンデント映画作家を支援する映画祭からの助成金をもとに製作しました。自分の故郷である北海道の札幌を舞台にした、高校生の男の子3人が主人公のいわゆる「青春映画」です。5人のスタッフとキャリアの浅い俳優たちと組み、僕自身で撮影も兼務したとても小さな映画で、『Playback』と同じくモノクロームの映画です。通常の劇場公開はされず、何度か特別な機会に上映されただけなので、商業的な意味では『Playback』が第一作目となります。
 『Playback』のシナリオのアイデアはどのように生まれましたか?
『Playback』のシナリオのアイデアはどのように生まれましたか?
三宅:まず、今作は僕にとって職業俳優たちと同じ現場で仕事をする初めての企画でした。しかも村上淳さん、それから渋川清彦さんなどは、僕が10代の頃から活躍していた憧れの存在でした。大きなチャレンジを前に「彼らと一緒に自分には何ができるのだろう?」と考え、そこから「そもそも俳優とはいったい何なのか?」と考えるようになったのがきっかけです。当初、企画書のタイトルは文字通り「俳優 The Actor」でした。
 その問いはどのようにシナリオに反映されたのでしょう?
その問いはどのようにシナリオに反映されたのでしょう?
三宅: 俳優とは何か、それはいまだに謎です。僕にわかったのは、彼らは毎日同じ台詞、同じアクションを何度も繰り返している人たちだ、ということだけです(たとえば何度も死んだりするのです)。にもかかわらず、彼らが俳優として存在する時間は、演じているその一瞬だけであり、すぐに消えてなくなってしまう。俳優というのはとても奇妙な人種で、また本質的に驚くほどもろくて、儚い存在なのかもしれない…。だからこそ、彼らが俳優として生きるほんの短い時間をなんとか捉えるために、ふさわしいシナリオを書き、撮影する必要があると考えました。
俳優という存在をそのまま物語の形式におとしこみ、彼らが生きるこの不条理な世界、その独特の時間をつくりだすというのがこのシナリオのチャレンジです。そのために、ある俳優を主人公にして、かつて彼が生きた時間——ここでは高校時代です——を、もう一度生きてもらうことにしました。つまり彼に自分の過去をふたたび演じてもらうわけです。しかも40歳近い俳優たちにはひげ面のまま学生服を着せました。というのも、「過去に戻る」という物語を深刻そうなドラマに仕立てるよりも、むしろ現実味がなくてナンセンスな側面、軽さや明るさを活かしたほうが、俳優の不条理な一面をよりうまく捉えられると考えたからです。だから『Playback』はジャンルでいえば、きっとファンタジー映画だといえます。
 つまりこれはタイムスリップの物語ですね。
つまりこれはタイムスリップの物語ですね。
三宅:そうですね。とくにアメリカ映画にはこの手の傑作がたくさんあります。フランシス・フォード・コッポラ『ペギー・スーの結婚』(86)、トニー・スコット『デジャヴ』(06)、あるいはハロルド・ライミス『恋はデジャ・ブ』(93)…。それらに比べると『Playback』はより抽象的ですが、やはりファンタジーのようなフィクションだからこそ感じられるリアリティやエモーションが絶対にあると思います。タイムスリップという物語が逆説的なかたちで教えてくれるのは、「あらゆる出来事は一度きりしか起こらない」、つまり「人生というのはたった一度きりしかない」という、ごく当たり前ながら切実な真実です。俳優とはまさにこの真実をもっともよく体現する存在です。彼らの存在を通して僕たちもまた、この不条理な世界に改めて気付くはずです。その出発点に立つことが、今作のひとつの目的かもしれません。
 なぜカラーではなくモノクロームを選択したのでしょう?
なぜカラーではなくモノクロームを選択したのでしょう?
三宅:モノクロームというのは、俳優の顔の潜在的な魅力をむき出しにするための可能性です。『Playback』の物語が俳優という存在の謎から出発した以上、まず何よりも彼らに寄り添い、彼らの力を引き出し、それを記録することが重要でした。また、カラーよりもモノクロームの方が、より純粋な仕方で「時間」そのものを意識させることができます。
それから『Playback』には実際に死者が登場します。それもモノクロームの選択に大きく関わっています。この映画では現在の世界と20年前の世界が描かれますが、当然、当時と変わらず生きている人々もいれば、その間に亡くなった人々もいます。両者の存在を同時に描くことが重要でした。つまり必然的に喪の作業というか、死んだ人間の物語が現れます。それを強調するためにモノクロームを選択しました。
 撮影の期間は何日でしたか? 苦労はしましたか?
撮影の期間は何日でしたか? 苦労はしましたか?
三宅:撮影は2011年6月末から7月頭。合計12日間でした。小さな予算で、タイトなスケジュールだったので、撮影はとても苦労しました。またぼくにとっては、これほど多くのスタッフ——とはいえ15人程度ですが!——と仕事をするのも初めての経験で、慣れるのに少し時間が必要でした。スタッフたちも奇妙なシナリオを渡されて不安だったでしょうが(笑)、撮影中は彼らのアイデアや技術に何度も助けられました。
撮影場所はほとんどが茨城県水戸市です。東京から車で北に2時間ほどの地方都市で、東日本大震災の被害が東京よりも大きい地域です。撮影当時は3月の大地震の数ヶ月後で、まだ大型の余震も頻発しており、放射能の問題に関しても一般への情報公開が隠蔽されたままで、極めて混乱した時期でした。そんな時期に映画製作をするという行為は、撮影に参加した全員に、ある種の緊張感をもたらしていたと思います。ロケ地のいたるところに震災の跡があり、それをカメラに収めるか否かも選択せねばなりませんでした。数多くの墓石が倒れ、破壊されたまま残っていたんです。
水戸に暮らすたくさんの方々がこの作品には協力してくれています。ロケハンの手助け、エキストラとしての参加、それからボランティアで僕たちのご飯を作ってくれた方々もいました。水戸で撮影できたことは本当に幸運でした。
 この作品ではスケートボードが重要な鍵となっていますが、
この作品ではスケートボードが重要な鍵となっていますが、
なぜスケートボードを選んだのでしょう?
三宅:それは主演俳優のおかげです。村上さんは、実はかつて俳優としてのキャリアを始める前はスケートボーダーでした。ただし、ここ10年以上スケボーには乗っていなかったとのことでした。でも僕は、40歳目前の彼がスケボーに乗る姿を想像すると、どうしても撮影したいと思ったんです。小さい頃から大好きだった『バック・トゥ・ザ・フューチャー 』シリーズ(ロバート・ゼメキス)を思い出しましたよ!
しかも、ロケハンの際に水戸市のはずれにハッとするような道を見つけたんです。新興住宅地の建設が財政的な理由により途中でストップしたまま放置された区域で、地震によってあちこちが隆起したままのアスファルトの道が、復旧されずに残っていました。その道にスケーターが立つ姿をイメージしたとき、この物語の始まりと終わりが決まったんです。
 俳優たちとの共同作業は、監督自身に何をもたらしましたか?
俳優たちとの共同作業は、監督自身に何をもたらしましたか?
三宅:俳優たちが積極的に普段とは別のチャレンジをしてくれました。彼らの衣装もほぼすべて自前ですし、あるシーンではインプロヴィゼーションもやってもらいました。それから村上さんは僕たちのロケハンに同行してくれて、さまざまなアイデアの交換もしました。「ロケハンに行くなんて生まれて初めてだ!」と、興奮していましたよ(笑)。
『Playback』は俳優について考える映画だと言いましたが、同時に、俳優たちに多くを教えられた映画でもあります。彼らとの共同作業によって改めて映画の本質的な力に触れられた気がします。クランクアップ後に、村上さんが「映画は生き物だね」と言ったことが印象に残っています。今後『Playback』がスクリーンにかかり多くの観客に観られることで、映画がどのように成長し、どのように年をとっていくのか、とても楽しみです。